このブログでは、Ranpak社のGeami WrapPak®という製品を使用して卵パックの落下実験をしています。
生卵はデリケートな商品なので、輸送の際には破損が生じないように丁寧に梱包することが大切となります。また、輸送する際に衝撃吸収性、安定性、環境への配慮が必要となります。
梱包した卵パックを1メートルほどの高さから落下させ「振動」と「衝撃」を与えて、卵に割れがないか確認しています。
紙緩衝材ソリューション
ブログ
私たちの生活に欠かせないプラスチック。
その利便性と環境負荷の両面について、特にマイクロプラスチック問題を通じて理解を深めることが、今、物流業界には求められています。
本ブログでは、マイクロプラスチックの基礎知識から、物流業界における具体的な課題、そして環境に配慮した包装材料の可能性まで、体系的に解説します。
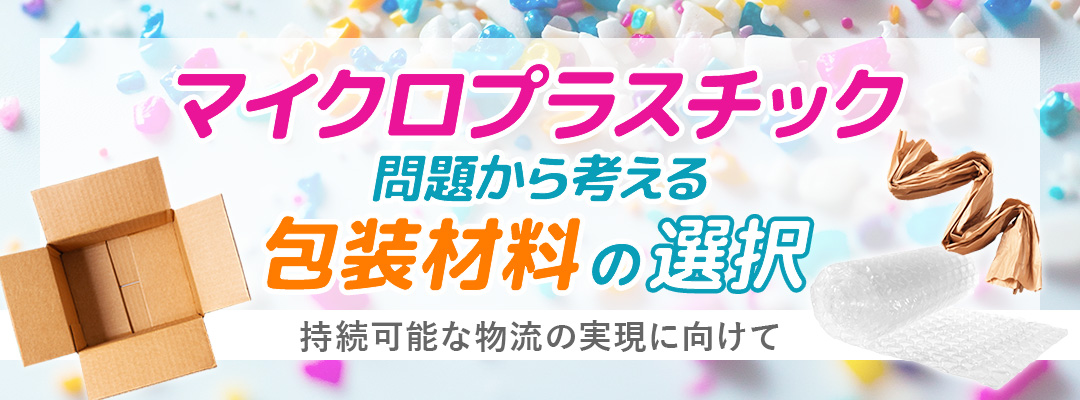
マイクロプラスチックは、5mm以下の微細なプラスチック粒子として定義され、現代社会における重要な環境問題として認識されています。
世界保健機関(WHO)[1]は、これを新たな環境衛生上の課題として位置づけており、特に大気中や飲料水中に広く存在する微細なプラスチック粒子への懸念を示しています。

マイクロプラスチックは、その発生過程によって二つに分類されます。
一次的マイクロプラスチックは、製造段階から5mm以下のサイズで生産されるものを指します。
これには、プラスチック製品の原料として使用される樹脂ペレットなども含まれます。
二次的マイクロプラスチックは、より大きなプラスチックが風や波などの物理的要因、あるいは紫外線や温度変化などの化学的要因によって細かく分解されたものを指します。特に海洋環境では、プラスチックの分解に数年から数百年もの時間を要することが知られています。
プラスチックは自然分解されにくい性質を持つため、環境中に長期間残存し続けます。
これらの微細なプラスチック片は、陸上でマイクロ化した後、最終的に海洋環境に流出し、深刻な環境汚染を引き起こしています。
このように、マイクロプラスチックは製造段階と環境中での分解の両方から発生し、現代社会が直面する重要な環境課題となっているのです。
以下は、プラスチックの主な種類と二次的マイクロプラスチックへのなりやすさをまとめたものです。
| プラスチックの種類 | 二次的マイクロプラスチックへのなりやすさ※ | 製品例 |
|---|---|---|
| ポリエチレン |
|
レジ袋 |
| ポリプロピレン |
|
ストロー |
| ポリスチレン |
|
食品トレー、発泡スチロールの箱 |
| ポリ塩化ビニル |
|
ホース |
| ポリエチレンテレフタレート |
|
ペットボトル |
| アクリル樹脂 |
|
水槽、定規 |
※プラスチックの種類が同じでも、製品によって二次的マイクロプラスチックになりやすいもの・なりにくいものがあります。
マイクロプラスチックが海洋生物に与える影響は、プラスチックの種類や生物種によってさまざまで、2020年時点では、427種類の魚でプラスチックの摂食が確認されており、マイクロプラスチックを摂取した魚は、消化機能に炎症反応が起きるなど物理的な影響を受けるほか、繁殖力や生存率が低下することが報告されています。[2]
マイクロプラスチックが人体に与える影響は大きく二つ考えられます。一つ目は、呼吸を通じた直接的な影響、もう一つは、魚などを介した間接的なマイクロプラスチックの摂取です。マイクロプラスチックは人体からも検出されており、人間が摂取していることは間違いありません。これまでは摂取されてもその大半は排泄されていると考えられていましたが、劣化プラスチックなどが人体に与える影響はまだまだ不確かなのが現状です。[3]
人体への具体的な影響については、研究の歴史が浅く、現時点では明確な結論は出ていませんが、その潜在的なリスクを考慮すると、完全に無害とは言い切れない状況です。

日本の物流業界におけるマイクロプラスチックの現状は、主に包装資材と輸送過程での発生に関連しています。
日本の物流業界では、商品保護や輸送効率の観点から、プラスチック製の包装材や緩衝材が広く使用されています。特に、Eコマースの急成長に伴い、個別配送用の包装材使用量が増加傾向にあります。
物流過程におけるマイクロプラスチックの発生は、主に以下の二つの要因に起因しています。
これらの課題に対し、日本の物流業界では以下のような対策が考えられます。
しかしながら、コスト面での課題や既存の物流システムとの整合性など、解決すべき問題も残されています。
今後は、環境負荷低減と物流効率の両立を目指した、さらなる技術革新や制度設計が求められています。
環境省が推進する「プラスチック資源循環戦略」[4]によると、企業に環境配慮型の包装材採用を求めています。
これを受け、多くの企業が再生可能な天然素材の活用や、リサイクル可能な包装設計への転換を進めています。梱包材の選択においては、商品の特性や輸送条件を考慮しながら、環境負荷低減と製品保護の両立を図ることが重要です。
環境負荷を低減する緩衝材として、プラスチック系緩衝材の代替製品のひとつとして紙系緩衝材が活用されています。
紙系緩衝材は以下のような優れた特徴を持っています。
生分解性が高く、
環境負荷を大きく低減できる
回収・再生のインフラが整備されている
様々な商品形状に対応可能で、
柔軟な設計が可能
再生可能な資源から製造可能
精密機器の梱包にも適している
企業ロゴや説明書きの印刷が容易
一方、プラスチック系梱包材を使用する際は、経済産業省の「容器包装リサイクル法」関連ガイドライン[5]に基づき、以下の点に留意する必要があります。
いかがでしたでしょうか。
本ブログではマイクロプラスチック問題を通じて物流業界に求められる環境負荷を低減する紙系緩衝材を紹介しました。
なお紙系緩衝材の衝撃吸収力については、輸送中に割れやすい生卵を例にして落下実験をしています。
以下参考ブログよりご確認いただければ幸いです。
最後までご覧いただきありがとうございました。
このブログでは、Ranpak社のGeami WrapPak®という製品を使用して卵パックの落下実験をしています。
生卵はデリケートな商品なので、輸送の際には破損が生じないように丁寧に梱包することが大切となります。また、輸送する際に衝撃吸収性、安定性、環境への配慮が必要となります。
梱包した卵パックを1メートルほどの高さから落下させ「振動」と「衝撃」を与えて、卵に割れがないか確認しています。
引用文献
[1] 世界保健機関(WHO)「Microplastics in drinking-water」
[2] 大塚佳臣ほか「マイクロプラスチック汚染研究の現状と課題」p.38|水環境学会誌 Vol.44, No.2
[3] 大気にも広がるマイクロプラスチック 海から空に拡散か 早稲田大などが健康影響も調査|東京新聞
[4] 環境省「プラスチック資源循環戦略」
[5] 経済産業省「容器包装リサイクル法」関連ガイドライン
その他参考情報
朝日新聞 SDGs ACTION!「マイクロプラスチックとは? 種類や人体への影響、問題と対策を解説」
(本ブログは、2025年2月27日執筆した内容です。)
PALTEKでは、環境に配慮したRanpak社の紙緩衝材ソリューションを紹介しています。
環境負荷の低減や梱包資材の保管費用等の削減を具体的に言及している採用事例詳細は以下をご覧ください。
株式会社ゲットイット様の声
『人件費も下がりました。保管料も下がりました。資材費も下がりました。環境負荷も下がりました』という評価に象徴されるように、複数の面で具体的な改善効果を実感しています。
現場からは『もっと早く導入すればよかった』という感想もあがっており、導入による高い満足度が伺えます。
※ご採用の声は、インタビュー時点の内容です。
