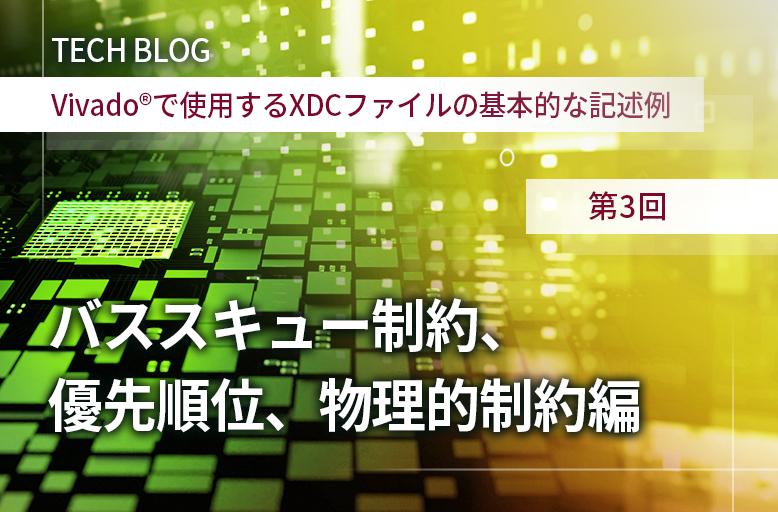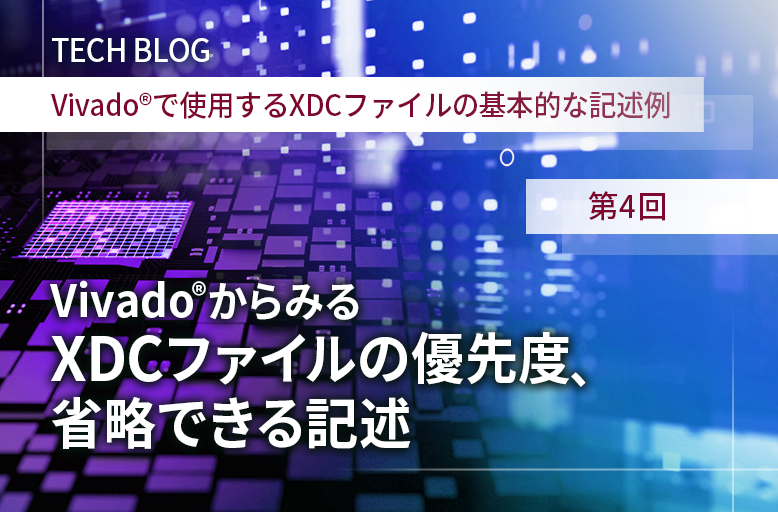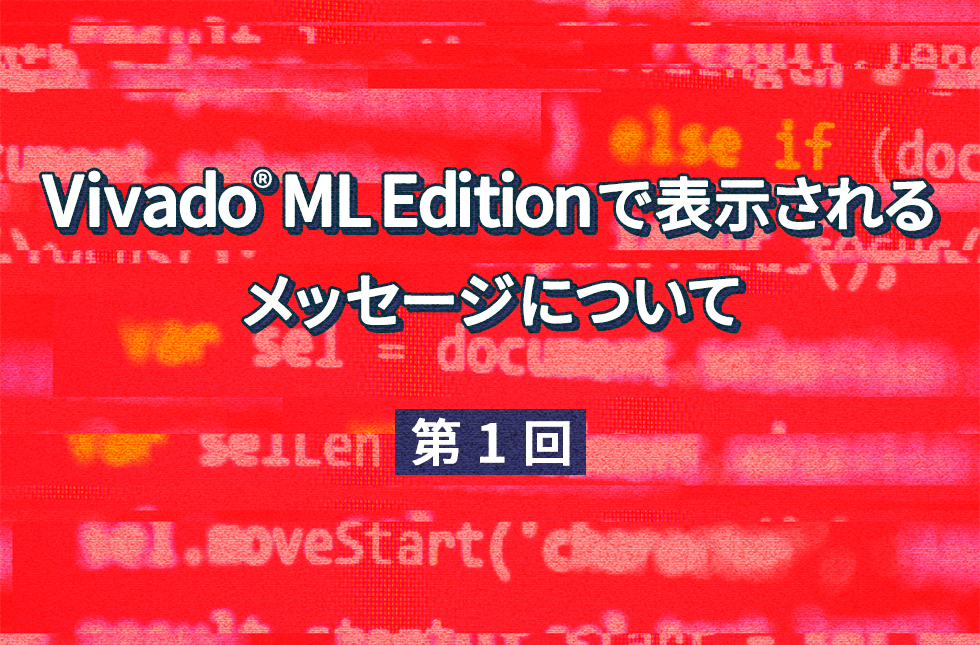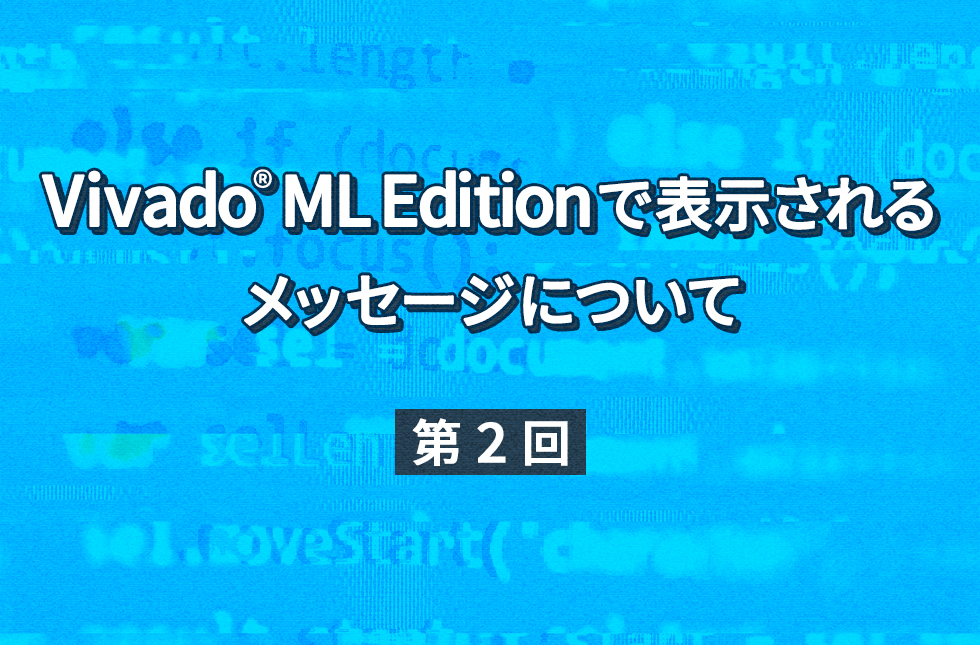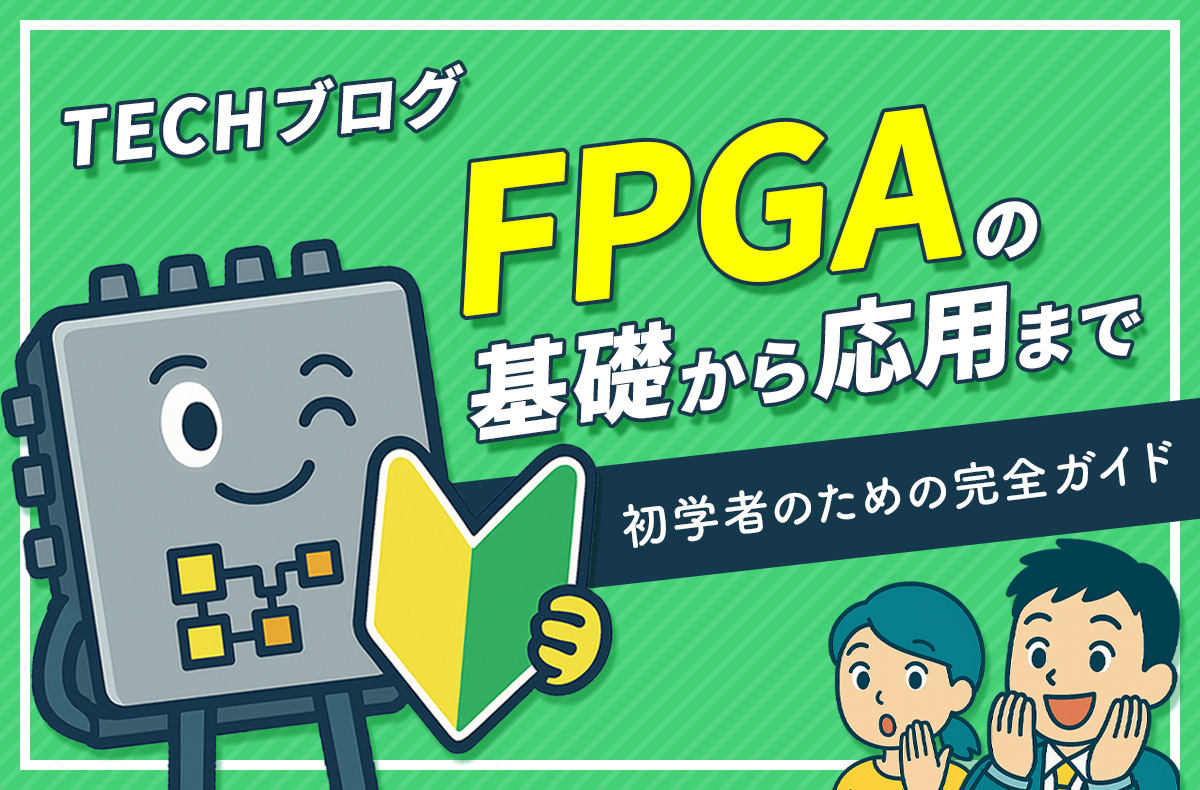【Vivado®で使用するXDCファイルの基本的な記述例】第1回 端子配置設定、クロック設定編

このブログでは、Vivado® ML Editionで使用する、「XDCファイル」の基本的な記述について解説します。
XDCとは、Xilinx Design Constraint(頭文字)の略です。
XDCファイルは、Xilinx社のFPGA及び適応型SoCに対して制約を与えることができるファイルで、以下の項目で制約設定が可能です。
- ・端子配置設定
- ・クロック設定
- ・コンフィグレーション設定
- ・タイミング設定 など
今回は、端子配置設定の中の、「端子配置設定」、「クロック設定」について説明します。
このブログは「FPGA設計ブログ一覧」の
4. インプリメント(配置配線)のひとつです。
目次
端子配置設定(端子配置、IO規格)
FPGA信号名“uart_txd”をFPGA端子“R21”に配置する場合の記述例
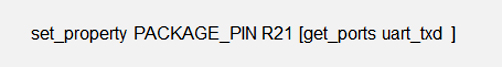
→get_portsコマンドで与えた文字列“uart_txd”を PACKAGE_PINプロパティの文字列“R21”にセットします。
BUS信号の場合、{}で囲む必要があります。
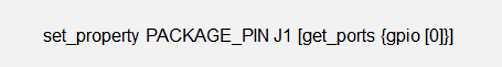
→get_portsコマンドで与えた文字列“gpio[0]”を PACKAGE_PINプロパティの文字列“J1”にセットします。
FPGA信号名“uart_txd”を“LVCMOS33”のIO規格制約を与える場合の記述例
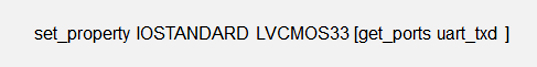
→get_portsコマンドで与えた文字列“uart_txd”をIOSTANDARDプロパティの文字列“LVCMOS33”をセットします。
※LVCMOS33→3.3Vバンクに対応します
BUS信号の場合、{}で囲む必要があります。
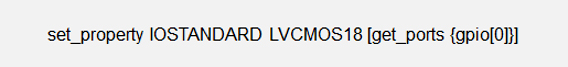
→get_portsコマンドで与えた文字列“gpio[0]”を IOSTANDARDプロパティの文字列“LVCMOS18”をセットします。
→IOSTANDARDは、ワイルドカードが使用できます。
※LVCMOS18→1.8Vバンクに対応します
他のIO規格として、以下の制約ができます。
シングルエンド規格LVCMOS12、LVCMOS15、LVCMOS18、LVCMOS25、LVCMOS33、LVTTL
差動規格
TMDS_33、LVDS、LVDS_25
SSTLやHSTL
SSTL15、SSTL18_I、SSTL18_II
HSTL_I、HSTL_II、HSTL_II_18
DIFF_SSTL15、DIFF_SSTL18_I、DIFF_SSTL18_II
DIFF_HSTL_I、DIFF_HSTL_I_18
DIFF_SSTL15_DCI
DIFF_HSTL_I_DCI
などがあります。
※SSTLは主にDDR用の制約、HSTLは汎用です。
端子配置、IO規格の制約は、1行で記載可能です。
全体を{}で囲みます。
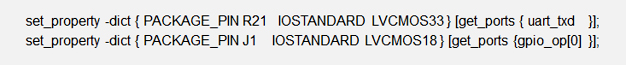
オプション設定
ドライブ強度[mA]
出力バッファの駆動電流を“mA”で指定します。
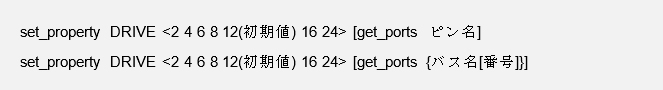
スルーレート
出力バッファのスルーレートを指定します。
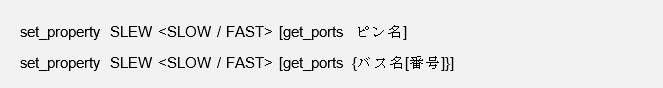
終端抵抗
差動入力、双方向バッファで使用する終端を指定します。
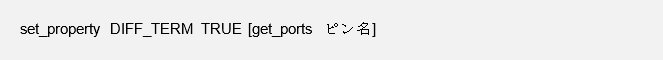
プルアップ・プルダウン
ウィーク プルアップ抵抗、ウィークプルダウン抵抗を有無の指定ができます。
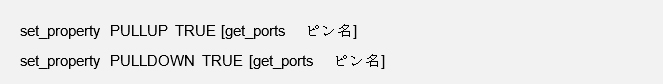
※TRUE→FALSEでディセーブルになる。
クロック設定
外部から入力するクロックの周波数を設定する。
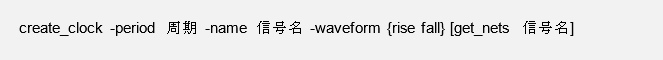
周期:“ns” or “MHz”で指定する。
→単位を指定しない場合、“ns”が適用される。
rise、fall:省略した場合、0ns/duty50%が適用される。
例1:100MHzのクロックの場合(信号名:clk100m)
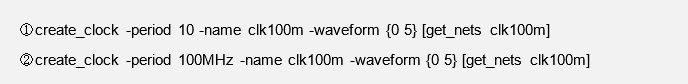
①が周期をnsで記載した場合
②が周期をHzで記載した場合
例2:125MHzのクロックの場合(信号名:clk125m)
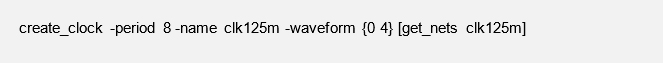
以上となります。
次回は、コンフィグレーション設定、タイミング設定について解説します。
このブログは「FPGA設計ブログ一覧」の
4. インプリメント(配置配線)のひとつです。
今回説明した内容でのご不明な点や、FPGA設計などでお困りのことなどがありましたら、下記よりお問い合わせください。